人生を変えるI amな本廃業寸前の本屋が予約の取れない「一万円選書」を生んだきっかけは? 斜陽産業でも「愛」と「豊富な知識」で生き残り。

読者から1万円を受け取って店主の「オススメ」の本を送る「一万円選書」。新発想の書店プロモーションを成功させたのは、北海道砂川市にある小さな書店の店主でした。
目次
「一万円選書」誕生のきっかけ
1990年、都市部の書店に勤務していた岩田徹さんは、故郷である北海道砂川市に戻り、父親が経営していた書店を継ぎました。38歳のことです。
岩田さんは、自分の理想とする書店を作るべく、借金をして店舗改装を行いました。その矢先にバブル崩壊。そして、長く続く出版不況に見舞われます。
本が売れない時代に本を売ろうと知恵を絞るも、決定打は出てきません。同窓会の席で岩田さんは、先輩に苦衷を打ち明けます。
その先輩は、巨大書店の進出で、選べないほどの本がある問題を指摘。どれが読むべき本か迷うばかりで、結局何も買わないまま書店を出るのだそう。
「だから、これで俺が面白いと思うような本を見繕って送ってくれないか。心がほっとするような本を送ってくれよ」と言いながら、先輩は岩田さんに1万円札を渡しました。岩田さんは、先輩の人柄や職業を考えながら10冊の本を選んで送ると、「いやー、面白かったよ! ありがとうと」絶賛されました。
このできごとをヒントに岩田さんは、1万円を受け取って「店主のオススメ」を送る、販売戦略を編み出します。
名づけて「一万円選書」。これは、テレビでの紹介をきっかけに大ブレーク。今や抽選制にしなければ、さばききれないほどの申し込みが来るそうです。
本が売れない時代に予約殺到の「一万円選書」とは
廃業寸前の店の経営を軌道に乗せた「一万円選書」。このシステムについては、岩田さんの著書『「一万円選書」でつながる架け橋 北海道の小さな町の本屋・いわた書店』(竹書房)にくわしく書かれています。
それをここで、細かく説明はしませんが、抽選で選ばれた人たちに、「何歳の時の自分が好きですか?」といったアンケートに回答してもらい、その内容を吟味して岩田さんは、本を選んで送付するというものです。
本書によれば、岩田さんが対応できる人数は、「年間で1200~1500人くらい」。それに対し、1万人近くの応募が来ることもあるそうです。観光ついでに店に足を運んで、選書を依頼してくる人もいるそうです。岩田さんはそういう人にも快く対応します。
一万円選書をしている最中に来店されたお客さんにいろいろと聞かれることもあります。「オススメの本はありますか?」「どんなジャンルが好きですか?」「この本は面白いですよ~」という接客が生まれます。実際に話しながらお客さんの好みに合いそうな本を選書してあげることも本屋としてすごく楽しい時間です(本書57pより)
こうした書店主冥利に尽きる記述が本書の中で続きますが、読んでつくづく思うのは、「本が売れない時代」でも、本という商品は売れる潜在力を持っているということです。
実際、一万円選書を支持する人は、若いスマホ世代が多いそうです。
魅力ある店作りは「本への愛」と「豊富な知識」
岩田さんは、「売れない理由なんて100でも言える」と書いていますが、売れる仕組みづくりがいかに大事か。出版不況を嘆く書店は、そのための工夫をしているか問いかけもします。
ここ数年、一万円選書で注目を浴びた岩田さんのもとには、大手書店グループから講演の依頼が来るようになり、また、全国から書店員が店に見学に訪れます。
一時、メガ書店の出店が相次ぎ、そのラッシュが一段落すると今度は、本が売れないという現実に直面。人口2万の街の小さな書店主の知恵にすがる逆転現象が起きているのです。
岩田さんは、「本を移動させ、並べてレジを打つだけ」「優秀な店員さんほど、夢がなくなった現場に絶望して辞めていく」という、大手書店の店員の働かせ方に苦言を呈します。
本屋なんてまさに人材命だと思います。本を愛し、本の知識が豊富な人たちによってこそ、魅力的な品揃えや棚作りが実現するんですから。
本が大好きな店員さんが去っていくお店に、本が好きなお客さんが来ると思いますか? 来ませんよ。だって本好きを刺激するような店作りができていないんですから。(本書137pより)
対して岩田さんの店は、書店員が「面白くてしょうがない」と言ってくれる職場。規模の大小を超えた、仕事とかやりがいの本質を垣間見せてくれる話ではないでしょうか。
このように、本書に散りばめられた様々なエピソードやアドバイスは、スモールビジネスを商う人々を鼓舞するパワーが秘められています。もしも今の仕事で壁に突き当たっているのなら、本書は貴重なヒントを与えてくれると思います。ぜひご一読ください。
関連記事
この記事を書いた人
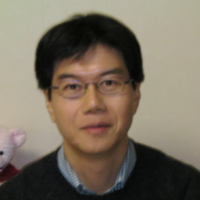
- 都内出版社などでの勤務を経て、北海道の老舗翻訳会社で15年間役員を務める。次期社長になるのが嫌だったのと、寒い土地が苦手で、スピンオフしてフリーランスライターに転向。最近は写真撮影に目覚め、そちらの道も模索する日々を送る。










