あなたの「脳番地」はどこが強い? 脳内科医が教える、自分がしんどくなる執着から解放されるシンプルな方法。

誰もが、いくつもの“執着”を抱えています。そしてそれが大きな悩みをもたらすこともあります。そんな執着の苦しみから抜け出す方法について、加藤プラチナクリニックの加藤俊徳院長に教わります。

プロフィール
脳内科医加藤俊徳
特定の物事にとらわれ、悩みをもたらす“執着”。脳科学の視点では、執着が起きるのは「脳番地」の使い方に問題があるからと説くのは、加藤俊徳院長(加藤プラチナクリニック)です。著書『悩みのループから解放される!「執着しない脳」のつくり方』(大和書房)の中で加藤院長は、よくある執着の対策を以下のように教えてくれます。
目次
人間には120の「脳番地」がある
脳には一千億を超える神経細胞が存在し、同じような働きをする神経細胞は、寄り集まって集団を作っています。各集団を、私は脳番地と呼んでいます。脳番地は約120ありますが、機能別に見ると、思考系、理解系、感情系、伝達系、運動系、視覚系、聴覚系、記憶系の8つに分かれます。
これらがまんべんなく発達している人はまれで、大抵の人は特定の脳番地が発達している一方、他は未成熟です。これが、何かに執着する原因となるとともに、解決のヒントにもなります。
長時間労働への執着を解決するには?
例えば、休みもとらず、毎日仕事に長時間取り組んでいる人は、自分の生活スタイルに執着しているといえます。
私の患者さんにもこういう人たちがいます。彼らは、「上司からのノルマ達成のプレッシャーが強く、やらなければ自分の居場所がなくなる」などと口にします。
仕事の疲れがたまっているなら、翌日に回し、今はゆっくり休めばいいはず。早めに就寝して朝早くから仕事をするなど工夫の余地もあるでしょう。なのに、なぜか夜更かししてしまうのです。これは、自分の生活スタイルを変えようとしない思考系脳番地に問題があります。
改善策の一つが、記憶系脳番地を強化するトレーニングです。それには予定を立て、そのタイムスケジュールに沿って行動をすることが効果的です。就寝時間から起床時間へと逆算して、〇時に入浴し、〇時に夕食をとり、〇時に退社するなどと細かく計画します。計画を紙に書き出して頭に入れたら、タイマーで確認しながら1日を過ごします。これによって未来の記憶をつくることにつながり、執着が薄れ、生産性も高まります。
他人が喜ぶことへの執着を手放すには?
人の期待に応えようとして疲れている人は、他人が喜ぶことに執着しています。「いい妻とはこうあるべき」といった思い込みに縛られた状態にあるのです。
「他人のために」は限度がなく、心は疲弊する一方です。また、「いい奥さん」「いいお母さん」のように執着の選択肢が多いせいで、それぞれについて理解系や思考系の脳番地を使って考える余裕を失っています。
これを解決するためにまず重要なのは、自分の時間を作って落ち着いて考え、元気を回復することです。体調が良くなれば周りの人も安心しますし、家族だってそうなることも望んでいるはずですから。
また、思考系脳番地のトレーニングをしましょう。朝一番に今日の目標を15字以内で考えることです。「職場の人に大きな声で挨拶する」「本を50ページ分読み進める」など、目標はどんなものでもかまいません。ただし、具体的な内容としてください。ちなみに、15字以内という制限があるのは、適切な表現や言葉を選ぼうとして思考系脳番地の活性化につながるからです。
お菓子がやめられない執着から解放されるには?
仕事中や夜中に、空腹でもないのになぜかお菓子を食べてしまう……。
これは疲れていて、脳の覚醒が低下していると起きやすい現象です。このとき、脳は思考できなくなり運動系脳番地を使いたがります。例えば、貧乏ゆすりや伸びがそうですが、口の筋肉を動かしたくなることもあります。それで余計なものを食べがちになるのです。
これは、お腹が空いているわけではなくて、体を動かしたいという欲求が、食べたいという欲求に変換されているだけなのです。そこで体を動かして、脳の覚醒を上げることが解決策となります。体を動かすといっても、散歩やストレッチのような軽い運動でも頭の働きは向上します。
もっと覚醒を上げる方法もあります。それは、インパクトのあるものを見て視覚系脳番地を鍛えることです。やりやすいのが、通勤・通学のルートを変えてみることです。いつもと違う道を通ることで、「新しいお店ができている」といった発見があったり、迷わないよう注意したりします。それが視覚系脳番地に刺激を与えるのです。また、歩きながら看板や標識に数字の7を見つけるというのも効果的です。
室内ではスポーツ観戦がいいでしょう。優れたプレーを目の当たりにすると、驚いて目が開きますが、これは覚醒が上がっている状態です。
関連記事
この記事を書いた人
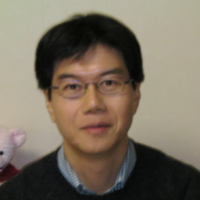
- 都内出版社などでの勤務を経て、北海道の老舗翻訳会社で15年間役員を務める。次期社長になるのが嫌だったのと、寒い土地が苦手で、スピンオフしてフリーランスライターに転向。最近は写真撮影に目覚め、そちらの道も模索する日々を送る。










