みらいのとびら 好きを仕事のするための文章術話しことばと書きことば 違いを知って使い分けると「伝える力」がアップする?
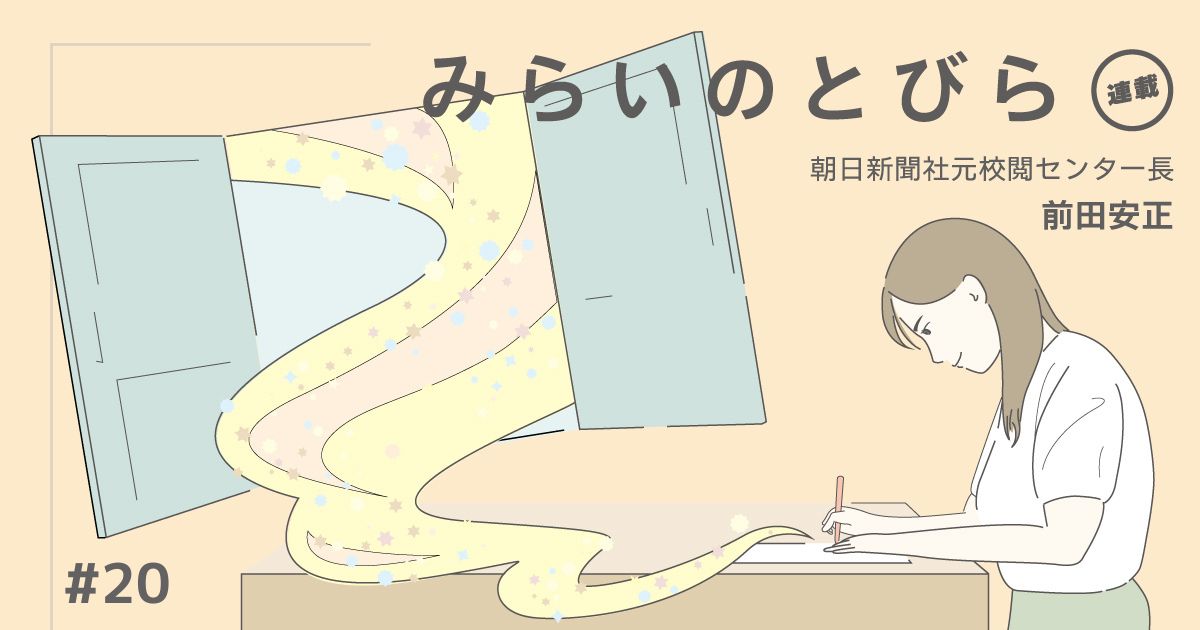
文章のプロ・前田安正氏が教える、好きを仕事にするための文章術講座。第20回は「話しことばと書きことばを使い分けたら、伝える力がアップする」についてです。
目次
自分で書いた漢字が読めない
大学の講座で、学生に自分のリポートを読んでもらいました。すると、自分で作成したにもかかわらず、そこにある漢字が読めません。パソコンを使ってリポートを書くと、自動的に漢字の変換候補があがってきます。学生は、それとおぼしき漢字を選択したものの、普段から使っていないので、読めないのです。
実は、これを他人事として笑ってはいられないのです。
いまは、パソコンやスマホで難しい漢字も簡単に出てきます。「書けなくても書ける」「読めなくても書ける」のです。ただ、身につかないことばを使うと、思わぬ「喜劇」が起きてしまいます。
劇作家に聞いた「話しことばと書きことばの違い」とは?
新聞社に勤めていた頃、改定常用漢字の特集ページをつくる機会がありました。常用漢字が大幅に増えるなかで、難しい漢字に頼らず平易に文章を書くことが重要だと思い、劇作家・演出家の平田オリザさんに話を聞きました。
平田さんは、「現代口語演劇理論」を提唱し、舞台上の会話もいわゆる芝居がかった台詞ではなく、自然な日本語を使っています。日常の静かで淡々とした営みの中にこそ、人間のドラマがあるという視点で演劇を実践しています。
「わかりやすい文章とはどういうものだと思うか」という僕の問いに、平田さんはこう答えてくれました。
「話すように書き、書くように話す」ことが重要だ。
それは「話すときは冗長になりがちなので、文章を書くときのように論理立てて話す。一方、文章を書くときは硬くなりがちなので、話すときのように柔らかく書く」という趣旨でした。
ところが、芝居の台詞については
「文でしゃべらず単語でしゃべれ」
と言うのです。「書くように話す」と矛盾しているように思えます。しかしこれは、舞台でのリアリティーの問題なのです。舞台での会話は、お互いが台詞として認識しているので、通常の会話とは異なります。つまり話す内容を双方がわかっていて、それを「会話に似せて」再現します。すると、舞台を見ている人にもわかるようにという意識が働いて、文章を読むような感覚で台詞を話してしまうからです。
ところが会話は、必ずしも全てが文として成り立たなくても伝わります。
「あ、猫だ」
「どこ?」
こんなふうに話しことばでは、単語でつながっていることが多いのです。これを
「猫がいる」
「どこに猫がいるの?」
とすると、会話のスピードとして成り立ちません。丁寧な物言いですが、どこか書きことばふうです。平田さんはこうしたことを指摘しているのです。
会話は、場が限られているので、相手に詳しい説明をしなくても状況がわかります。しかも文法に縛られることがありません。
「痛い、引っかかれた。この猫なに?」
会話では、語順がバラバラでもじゅうぶん伝わります。ところが面白いことに、一番言いたいこと、伝えたいことから、話し出すのです。それが、会話の特徴です。
しかし書きことばでは、
「この猫に引っかかれたので、手が痛い。いったいこの猫はどうしたというのだろう」
こういう具合になります。表現の仕方は他にもあると思いますが、少なくとも手順を追って読み手に伝えていくという手法をとることになります。

話しことばが失言を生みだす理由
さらに会話では、枝葉がどんどん広がっていきます。
「風が吹けば桶屋が儲かる」は、小さな出来事が巡り巡って意外なところに影響するという一種のバタフライエフェクトのように使われるたとえです。
風が吹くと、土埃が舞い、それが目に入って眼病を患う人が増える。その人たちが生計を立てるために三味線が必要になる。そのため三味線の革に必要な猫が捕獲されるので、町中から猫が減りネズミが増える。増えたネズミが桶をかじり使い物にならなくなる。すると桶屋が儲かる。これは江戸時代の浮世草子から出た話なので、現代の感覚とは異なります。しかし、風の話から桶屋の話にいたる展開は、話しことばのそれと似ています。
会話はおしゃべりとして、こうした枝葉に話が広がることが一つの楽しみでもあります。とはいえ、直感的・瞬発的な展開が多い会話は、話が整理されないままその場その場の対応で進みます。結局、伝えたいことばを見失い、長話になります。長話の割に、内容がないことも多いのです。
また、「笑いを取ろう」とか聞き手の反応を見て、直感的にことばを発するので、枝葉の部分が誇張されたり、失言を生み出したりしがちです。書くことと同様、話すことの訓練を受けていない僕たちは、どうしてもことばと向き合う機会が少なく、ときに的確なことばを失ってしまうのです。
やはり「書くように話す」ことは、必要なのです。
書きことばでは「幹」を意識すると伝わる
一方、文章は極力、枝葉を排して、幹を書かなくてはなりません。焦点をグッと絞って書かないと読み手の集中力を削いでしまいます。『老人と海』の著者ヘミングウェイが新聞社時代に教わった文章の書き方は、
・文は短く、最初の段落は短く。
・気持ちの入ったことばを使え。
・自信を持って書け、逃げ腰になるな。
・無駄なことばは全部削れ。
(引用:ヘミングウェイスペシャルNHK100分で名著・都甲幸治早稲田大学教授から)
でした。
「無駄なことばは全部削れ」。これが、枝葉の広がりを抑えて幹をしっかり書き込む際に、最も重要なポイントです。文章は書き足すことは比較的簡単です。しかし、書いたものを絞り込む作業は、文を短く書くことよりも難しい作業です。
それは、自分で書いた文章のどこが枝葉なのかが、わからないからです。これには、編集の視点が必要になります。何が必要で何が無駄なことばなのか、を見極めるには、自らの文章を客観的に俯瞰しなくてはならないからです。
たとえ無駄な部分がわかったとしても、それをどう削ればいいかがわかりません。ばっさり削っていい場合もあります。一方で、書いた意図を汲んだうえで、ことばを精査し整えることが求められる場合もあります。
こうなると、がんじがらめになって「文章を書くのは難しい」ということになります。また、文章を論理的に書かなくてはならない、という思いが先行すると、文章とはこうあるべきだという既成概念の尻尾を引きずってしまいます。取って付けたような、納まりのいい文章が論理的だと勘違いしてしまうのです。
そうすると、普段使い慣れていない妙に難しいことばを使ったり、丁寧に書こうとするあまり何度も同じことを書いてしまったりします。
これでは「気持ちの入ったことば」を使うことにはならないし、「自信を持って書く」こともできません。「〜である」と言い切れず、「〜ではないだろうか」などと語尾を濁らせて「逃げ腰」のことばを使ってしまいます。これでは、説得力のある文章にはなりません。

「無駄なことばを徹底的に削ろう」と言うと、必ず「文章表現の豊かさがなくなる」「個性が消える」という反論を受けます。そういう反論をすること自体が、文章に対する既成概念の尻尾を引きずっている証左です。無駄なことばを削ることは、必要なことばを残し、明瞭にするということです。無駄なことばのなかに「表現の豊かさ」や「個性」が宿っているはずがありません。
「無駄なことばを徹底的に削る」ということは、わかりやすく簡潔に書くということです。そこには必ず「表現の豊かさ」と「個性」が残ります。
こうしたアプローチを経て「話すように書く」ことができるのです。
このコラムを読んでいるあなたは、副業や起業を目論んでいたり、その道を進んでいたりするかもしれません。そうしたときに、あなたのサービスや商品について「自信を持って伝える」ことは、とても重要な働きを持ちます。
会話が情緒を中心にした枝葉のコミュニケーションであれば、文章は論理を中心にした幹のコミュニケーションです。それぞれの特性を活かした伝達手段を使いこなせるようにして、可能性を大きく広げていきましょう。
執筆/文筆家・前田安正
関連記事
この記事を書いた人

- 未來交創代表/文筆家/朝日新聞元校閲センター長
-
早稲田大学卒業、事業構想大学院大学修了。
大学卒業後、朝日新聞社入社。朝日新聞元校閲センター長・元用語幹事などを歴任。紙面で、ことばや漢字に関するコラム・エッセイを十数年執筆していた。著書は 10万部を突破した『マジ文章書けないんだけど』(大和書房)など多数、累計約30万部。
2019年2月「ことばで未来の扉を開き、自らがメディアになる」をミッションに、文章コンサルティングファーム 未來交創株式会社を設立。ことばで未来の扉を開くライティングセミナー「マジ文アカデミー」を主宰。










