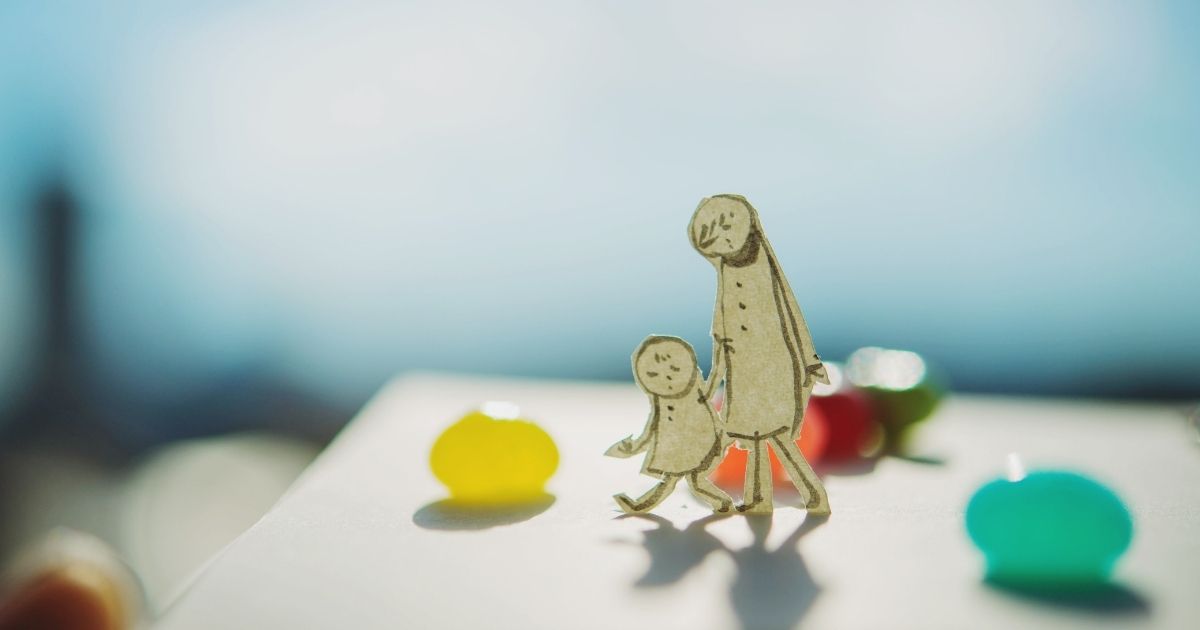小学3年生の娘の宣言「私、学校をやめる」。教育学者が直面した我が子の不登校。親子の対話でわかったこととは?

哲学者で教育学者の苫野一徳氏の提案する哲学対話。哲学思考を親子の対話に取り入れることで、子供の不登校を乗り越えた実体験とは?
小中学生の不登校は年々増加し、令和4年は過去最高の29万9048人になりました。哲学者で教育学者の苫野一徳さんも、長女の不登校を体験した一人です。これがきっかけで出版した『親子で哲学対話ー10分からはじめる「本質を考える」レッスン』を紐解きたいと思います。
【写真】親子で哲学対話ー10分からはじめる「本質を考える」レッスン
「長女が小学校4年生のとき、私に突然、『パパ、寝る前にちょっと哲学対話やるよ』と言ってきたことがありました。 哲学者の父としては、願ってもないことです。『おお、ついに娘がパパの仕事に興味を持ち始めたか』と、思わずニヤリとしました」
しかし、嬉しさとは裏腹に一つの考えが頭をよぎります。なぜなら、「その一年前、小学校3年生のとき、娘は約半年間、不登校になりました。いや、当時の彼女の言葉を借りれば、『学校をやめた』からです。
「数ヶ月、娘は、一見楽しそうに学校に通ってはいたのですが、夜になるといろんな不安がやってくるようで、しばしば泣いていました。そしてある頃から、学校には行きたくないと言い出し、しばらくして突然、『パパ、ママ、私、学校やめたから』と宣言してきたのです。」
そんな書き出しから始まる『親子で哲学対話ー10分からはじめる「本質を考える」レッスン』の著者、苫野一徳さんは、哲学者であり教育学者。熊本大学の准教授として教鞭を執る2児の父です。
文部科学省によると小中学生の不登校は小学生は10万5113人、中学生は19万3936人で計29万9049人で、過去最高の数字に。
*令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた緊急対策等について(通知)より
不登校は子ども自身の苦しみに加え、家庭教育の負担も大きいと言われています。不登校の生徒を受け入れるフリースクールの数が増えてきたとはいえ、全国2万2000の小学校(公立、私立含む)に比べると500に満たないのが現状。
「親の負担についても、思うところはたくさんありました。 私たち夫婦も、当初思っていた以上の大変さを味わいました。一日中、子どもの面倒を見られる家庭というのは、現代の日本にはそう多くはないんじゃないかと思います。」と苫野さんも本の中で認めています。
大学教授ということもあり、長女が不登校の間に自身の職場である大学に連れていくことに。長女はキャンパスや研究室で他の教員や学生たちと「交流」を持ち、「友達」を作ることができたといいます。
しかし、多くの不登校の子どもたちがそうであるように、彼女の苦しみもまた深いものだったと……。
「学校に行かなくなった分、娘には、一人で悶々と悩み続ける時間がますます増えていきました。学校に行けなくなったのは、自分が弱いからではないか、自分が悪いのではないか、自分はダメな人間なんじゃないか……。どれだけ親が、そんなことを思う必要はまったくないと陰に陽に伝えても、娘はそう考えて、どんどん落ち込んでいったのでした。 生きるってなんだろう、強さってなんだろう、学校ってなんだろう、友だちってなんだろう……。そんなことを、毎日、考え、悩み続けていたようです。」
結果的に半年で学校に戻ることになったのですが、学校に戻ってしばらくたって、「パパ、寝る前にちょっと哲学対話やるよ」という長女の言葉で「親子で哲学対話」がスタートしました。
哲学対話とは、ものごとの本質を言葉にして編み上げていく哲学の思考法「本質観取」のことを指します。聞き馴染みのない言葉ですが、読んで字の如く「本質を観て取る」こと。哲学対話は「ソクラテス式対話」とも呼ばれ、長い哲学の歴史の中で培われてきた思考法です。
「物事の本質とは何か?」を問う時に、対話によって思考を深めていく。
「愛とは何か」
「時間とは何か」
「存在とは何か」
「悪とは何か」
哲学2500年の歴史において、これら哲学的な問いに答えを出すために使われてきた思考法。
哲学対話は2人、ないしは数人で、ある一つの問いに対して、それぞれが具体的な体験や経験を持ち寄り、共通了解を見出し、言語化していくというプロセスです。
最初から絶対的な正解や真理があるわけではなく、みんなが「なるほど、それは確かに言えてる、本質的だ!」という納得に辿り着くこと。正解ではなく本質に近づくという点がポイントです。
この「本質を考える力」が「哲学の力」そのものなのかもしれません。
ちなみに本書には苫野さんと長女の実際の哲学対話は20編が収録されています。「ファッションと校則」「かわいい」という小学女子らしいものから、「思いやり」や「よい行い」といった道徳的なテーマ、さらには「人間の愚かさ」や「大人とは」というドキッとするものまで、親子で挑んだ哲学的問いが並びます。
夜一人で泣きながら「学校をやめる」と決断した少女の目に映る社会(学校)。「子どもの思考力を侮ってはいけない」と言うように、その洞察力と思考力は大人の想像を超えています。
不登校、そして親子で哲学対話を経て、長女がある時口にした「あれはよかった」という言葉。父としてより、哲学者としてとても嬉しかったそうです。
というのも、誰でもアクセスできる「役に立つ哲学」を目指して活動してきた苫野さんは、草の根で哲学対話のワークショップを企業向けや小学生の子ども向けなどに開催してきました。子どもでも対話を通して飛躍的に思考力、対話力が高まっていくと言います。
たった10分、焦らずせかさず、子どもと向き合う時間を作ってみてはどうでしょうか。
苫野一徳さんと子ども達との哲学対話のデモンストレーションイベントがオンラインで開催されます。哲学対話の具体的な方法を学ぶことができます。
文/長谷川恵子
関連記事
この記事を書いた人

- 編集長
- 猫と食べることが大好き。将来は猫カフェを作りたい(本気)。書籍編集者歴が長い。強み:思い付きで行動できる。勝手に人のプロデュースをしたり、コンサルティングをする癖がある。弱み:数字に弱い。おおざっぱなので細かい作業が苦手。