人生を変えるI amな本21世紀の今こそ知っておきたいチャップリン入門

人生が変わる I am な本。今回は大野裕之さん新刊『ビジネスと人生に効く 教養としてのチャップリン』(大和書房)を紹介。
目次
「喜劇王」として映画史上に名を残す、チャールズ・チャップリン
今年没後45年、全国各地で「フォーエバー・チャップリン ~チャールズ・チャップリン映画祭~」も開催され、あらためて話題を呼んでいる喜劇王・チャールズ・チャップリン。
チャップリンといえば、だぶだぶのズボンをはき、ステッキを持ち、山高帽をかぶった、コミカルな姿を思い浮かべる人が多いでしょう。ですが、彼の映画を観たことがある人は、少なくなってきているかもしれません。これを書いている筆者も、それ相応の年齢になりましたが、十代の頃に名作『街の灯』を見たという記憶が、かすかにあるだけです。

しかし、第75回カンヌ国際映画祭でウクライナのゼレンスキー大統領は、『独裁者』を引き合いに「新たなチャップリンが必要だ」と訴え、レディ・ガガはコロナ禍のさなかに、チャップリン作曲の名曲「スマイル」を歌いました。そう、チャップリンは21世紀の今も、時を超えて人々に求められているのです。むしろ、混迷を極めた今のような時代にこそ、われわれはチャップリンをよく知るべきなのかもしれません。そこで今回は、新刊『ビジネスと人生に効く 教養としてのチャップリン』(大和書房)より、チャップリンの新たな一面と魅力を紹介したいと思います。
史上初の世界的にバズった人物はこうして生まれた
チャップリンが生まれたのは、1889年4月16日。出生の地は、ロンドン郊外の貧困地区でした。そこは、子供の3人に1人が5歳になるまでに命を落とす過酷な環境でした。

両親は寸劇などを上演するミュージックホールの芸人として活躍。チャップリンが生まれた頃は、暮らし向きは比較的良かったようです。しかし、彼が2歳の頃、両親が別居。父は酒に溺れて仕送りも滞り、母は健康を崩しがちとなり、極貧生活に陥ります。そのような極限状態の中で、チャップリンは俳優としての能力を開花させます。初舞台は5歳。芸人だった母親が本番中、舞台上で声がうまく出なくなるトラブルに見舞われます。困った劇場主は、苦肉の策として息子のチャップリンを舞台に送り出しました。
チャップリンは見よう見まねで歌い踊り、さらには無意識のうちに母ハンナのしゃがれ声まで真似て笑いを取りました。可愛い子供のステージに酔客たちは拍手喝采して、たくさんの投げ銭が飛んできました。チャップリン少年が思わず、「続きはお金を拾ってから歌います」と言ったことで、一層客は沸きました。こうして、チャップリンは 5 歳にして喝采の味を覚えたのでした。(本書 36~37p より)
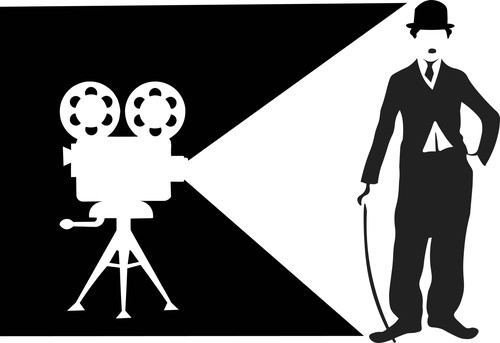
一大転機が訪れたのは1913年のことです。アメリカでの巡業公演中に、当時新興メディアだった映画界から、スカウトがあったのです。映画会社に提示された週給は150ドル。彼が当時所属していた劇団の2倍の額です。チャップリンは、3ヶ月後から週給175ドルにするという条件で、映画デビューを果たすことになりました。デビュー作は『成功争い』という作品で、2人の男が新聞社で特ダネを争うドタバタ喜劇でした。このときの彼は、まだあのチョビ髭姿ではなく、ドジョウ髭にフロックコートという扮装で、ペテン師を演じています。
トレードマークともいうべき「放浪紳士」の扮装が生まれたのは1914年。『メイベルのおかしな災難』という作品を撮影中のことでした。監督から突然、「何か喜劇の扮装をしてこい、なんでもいいから」と言われ、衣裳部屋に行く間に、おなじみの扮装を思いつきます。着替えてチョビ髭をつけ、メイクをしたときには、もうあのキャラクターが生まれていたといいます。チャップリンはその後四半世紀にわたり、衣裳をほとんど変えることなく、「放浪紳士チャーリー」を演じ続けました。
映画のためなら靴を 63 回食べる?
チャップリンは所属する映画会社を変えながら、そのたびにサラリーが増え、わずか数年で(現在の円に換算して)年収約20億円という世界的大スターとなりました。その頃には監督や脚本も担当するようになり、マルチな才能を発揮します。
1918年には独立して自前の撮影所を設立しました。そこから、『街の灯』『黄金狂時代』『モダン・タイムス』『独裁者』といった、数々の不朽の名作を生み出します。

大野さんは本書のなかで、主要作品の背景について解説しています。そこで語られるエピソードに共通するのは、チャップリンの徹底的に完璧を求める姿勢。たとえば、『黄金狂時代』では、空腹のあまり革靴を食べるという有名なシーンがあります。納得のいく画が撮れるまで、チャップリンは甘草でできた靴をなんと63回食べたそうです。
膨大なNGシーンを残しながら撮り直しするうちに、設定や内容が全く変わってしまうことも稀ではありませんでした。しかし、この試行錯誤の末に内容がどんどん洗練されていき、今われわれが観ることができる、素晴らしい作品へと昇華していったのです。
ミッキーマウスのモチーフはチャップリン?!
本書には、映画を観ただけでは知ることができない、チャップリンの知られざる一面も紹介されています。たとえば、未発表の論文「経済解決論」では、1931年の時点で、ワークシェアリング、自由貿易、欧州の通貨統合を提案しています。彼がこの論文を書いたのは、世界旅行の途上。この旅行では当代きっての政治家や文化人らと面会し、対話を繰り返して様々な分野の知見を深めました。

親交があった著名人の中で意外ともいえるのが、ウォルト・ディズニーとの関係です。実は二人は事実上の師弟関係にありました。ディズニーにとって、12歳年上のチャップリンは憧れの存在でした。彼は、小学生の時になんと「チャップリンものまねコンテスト」に優勝して賞金を得ています。当初は俳優の道を志したディズニーでしたが、その才能に見切りをつけ、アニメの世界へ進みます。彼が、チャップリンと初めて会ったのは1930年初頭。そのときの様子が、次のように書かれています。
喜劇王に「僕も君のファンだよ」と言われたことで彼は有頂天になります。同時に、チャップリンは自分の他に若い天才が現れたことを見抜いて、現実的な忠告も忘れませんでした。「だけど、君が自立を守っていくには、僕がやったようにしなきゃ。つまり、自分の作品の権利は他人の手に渡しちゃだめだ。」
ウォルトはこの忠告を生涯守りました。今もディズニー社は作品の著作権やキャラクターの権利を厳格に守って活用していますが、そのきっかけはチャップリンの一言だったのです。(本書 154~155p より)
実はチャップリンは、自分の扮装をマネするものまね芸人が多発したことに対して、1917年に裁判を起こして勝利しています。世界で初めてキャラクターの肖像権を認めさせ、知的財産権を確立したチャップリンは、自分と同じような経験をさせないよう、ディズニーにアドバイスしたのです。
ミッキーマウスの姿形は、チャーリーに大きな影響を受けているとディズニー自身が語っています。彼はそれほど、チャップリンをリスペクトしていました。
チャップリンを見れば未来がわかる

チャップリンが遺した映画は80本余りにおよびますが、単なる名作映画とはいえない「新しさ」に満ちています。
著者の大野さんは、一例としてリアルな格差社会の描写を挙げています。『勇敢』という初期の作品には、地下室のシーンが出てきますが、そこでは麻薬中毒者が登場します。これは「映画史上初めて薬物が書かれたシーン」でもありますが、さらに注目すべきは次の点です。
『勇敢』で注目したいのは、普通に人が住んでいるところの壁一枚隔てたところに薬物があるという描写です。集合住宅の地下に中毒者がいる設定は、貧困からさらに転がり落ちた先に薬物があるということを象徴的に図示しており、現代の格差社会とその結果を見通しています。(本書184pより)
さらに、代表作の『モダン・タイムス』や『独裁者』では、労働者やユダヤ人といった弱者が、知らないうちに権力に取り込まれ、半ばその状況に満足してしまっている様子が描かれています。これも格差社会のリアルであると大野さんは指摘しています。

一方、晩年に撮られた最後の主演作『ニューヨークの王様』で、チャップリンはクー・デタによってアメリカに亡命した国王の役を演じています。国王は、パーティーに出席していると思いきや知らないうちに「リアル・ライフ・サプライズ・パーティー」なるテレビ番組に出演させられていた、という現代のリアリティショーのような場面もあります。
このように、チャップリンの映画には、今なお問題となっている社会的課題、あるいは最近の流行まで予見したかのようなシーンがいくつも見られ、それだけでも単なるコメディ映画を超えた作品といえるのです。
ここではすべてを紹介できませんが、本書にはチャップリンを知り、現代を知るヒントとなる様々な知見が盛り込まれています。年末年始の読書の1冊として手にとってみてはいかがでしょうか?
| 書名 | 教養としてのチャップリン |
| 著者 | 大野 裕之 |
| 出版社 | 大和書房 |
| 出版年月日 | 2022/11/2 |
| ISBN | 9784479393962 |
| 判型・ページ数 | 4-6・288ページ |
| 定価 | 1,760円(本体1,600円+税) |
関連記事
この記事を書いた人
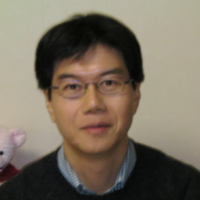
- 都内出版社などでの勤務を経て、北海道の老舗翻訳会社で15年間役員を務める。次期社長になるのが嫌だったのと、寒い土地が苦手で、スピンオフしてフリーランスライターに転向。最近は写真撮影に目覚め、そちらの道も模索する日々を送る。





