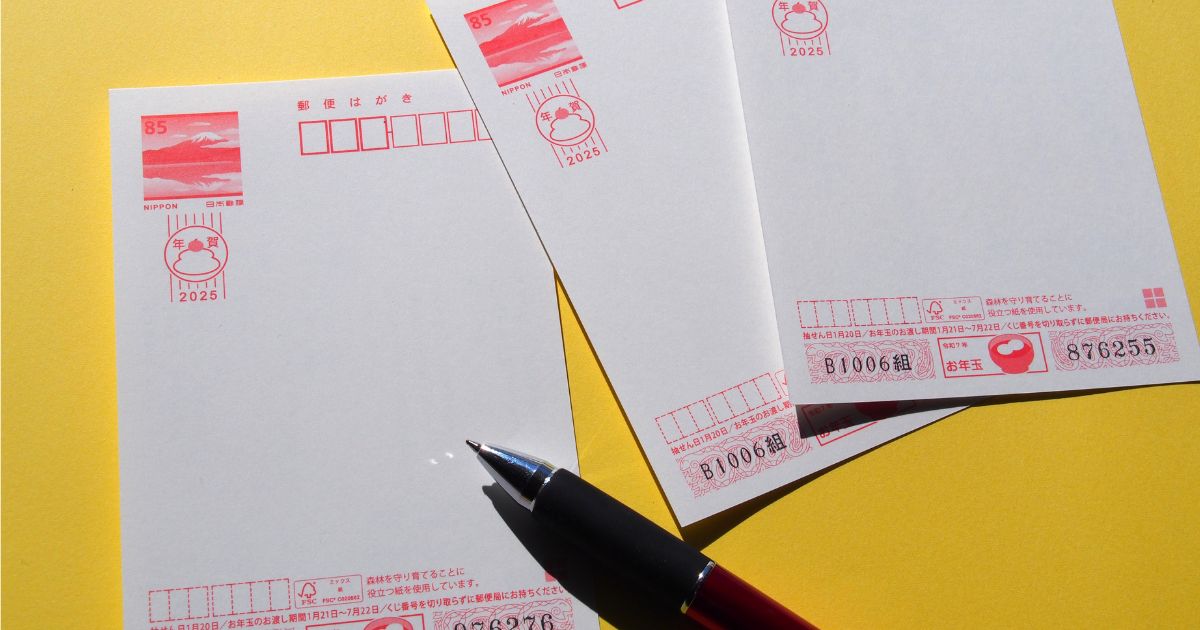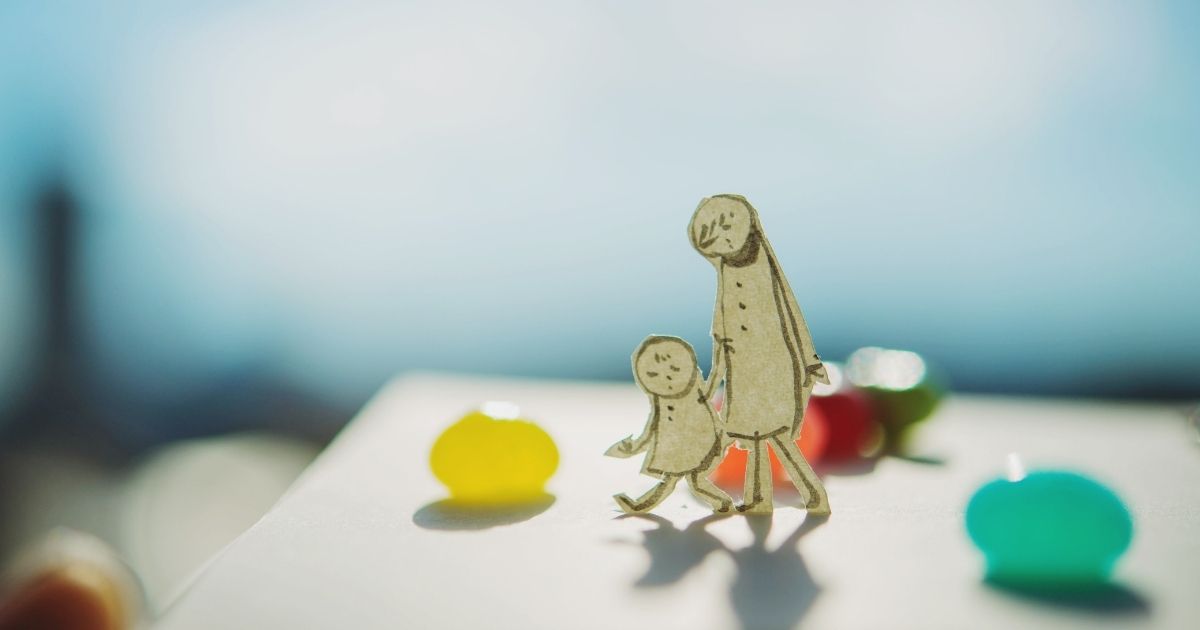精神科医が教える、リモートワークのデメリット。疲労をためないコミュニケーションの取り方とは?

デジタル化が進む今の社会、「休んでもなぜか疲れが抜けない」という人が最近増えています。その原因と対策について、早稲田大学教授・精神科医の西多昌規さんに教わります。

プロフィール
早稲田大学教授、精神科医西多昌規
リモートワークやDXの時代は、常時接続のコミュニケーションとなりやすく、いつの間にか疲労が蓄積しています。ではどうすれば、その問題を解決できるでしょうか? 『休む技術2』(大和書房)の著者、早稲田大学教授・精神科医の西多昌規さんが、そのコツをお伝えします。
目次
休日は、朝だけメールチェック
休んでもなぜか疲れが抜けない原因は、いろいろ考えられます。その一つとして、勤務時間外や休みの日も、仕事のメールをチェックしていることが挙げられます。
私の場合、1日に平均して100通ぐらいはメールを受け取っています。だから、休日だからと丸1日メールをチェックしないというのは、考えただけでもぞっとします。本当は、休日はメールをチェックしないのが、疲れを抜くという点では正解です。ですが、休日明けのメールの数を思うと、精神的には休めないのです。
これは何も日本人だけの問題ではなく、海外でも同様です。フランスでは、その対策として勤務時間外や休日の業務連絡を拒否できる「つながらない権利」を認める法律が施行されているくらいです。日本でも一部の企業が、長期休暇中のメールを受信拒否・自動削除できるシステムを導入しています。
もし、日本人の全員に「つながらない権利」が認められ、その行使が推奨されたらどうなるでしょうか。「明日の朝、ものすごい数のメールがたまってそう」という予期不安で、かえってスッキリしない休日になってしまうかもしれませんね。
そこでおすすめしたいのが、休日の朝だけメールチェックをしておくという、割り切った考え方です。そのときは、どうしても返信しておきたいものだけ返信しておいて、あとは翌日に回します。こうすれば気持ちはスッキリしますし、小さな達成感も得られます。
チャットは即レスより、既読スタンプで
最近は、Slackに代表されるビジネスチャットツールが普及しています。
とても便利なのですが、頭の痛い問題があります。それは即レスの是非。なにか連絡や通知があったら、すぐにレスポンスしなければと焦ってしまうのです。
こうしたアプリを使うと、レスが早い→仕事ができる、やる気があるという評価になりがちです。レスが遅いと、イライラするタイプの相手も多いでしょう。しかし、何か来るたびに即レスしていては、仕事の腰を折られ、また初めからエンジンをかけなおすというデメリットがあります。
まず、考えておきたいのは、即レス自体が目的になっていないかという点です。とにかく早く返信して、内容の質は二の次となってしまえば、相手は望む情報を得られず本末転倒となるおそれがあります。
また、なかなか返事が来なくて、相手を不安にさせるのがいやであれば、不安にさせないことに力点を置きます。つまり、とりあえずいつまでに連絡するとだけ伝える、あるいはリアクションスタンプを押しておくのですね。SlackはLINEと違って、読んだだけでは既読とならないので、能動的にスタンプを押しましょう。
リアルなコミュニケーションが疲れを癒す
リモートワークだと、仕事上の人とのやり取りもすべてオンラインで済ませられて便利です。
ですが、人と直接会うリアルなコミュニケーションもしてほしいです。それが、心と身体のリズムを整え、疲れを癒す一つの方法になるからです。
人間関係に疲れて、人と会うのはしばらくお休みしたいという人もいるでしょう。しかし、孤独も長引くと、健康を損ないますし、心にもぽっかり穴をあけてしまいます。可能な範囲で毎日誰かと話せる環境をつくっておくべきです。
少し話が変わりますが、日中にやりたいことを我慢するほど、夜のスマホの使用時間が増えるという研究結果があります。心の中では人と接したいという欲求があっても、それが満たせない環境では、夜のスマホに向かわせる可能性があると思います。それで睡眠の質が下がって、日中の疲労感につながる恐れがあります。
会ってのリアルでのコミュニケーションがなかなかできないのであれば、SNSやチャットでやりとりするだけでも、だいぶ違います。「最近どう?」で始まる何気ない雑談でも、メンタルの安定をもたらしてくれます。手段はどうあれ、日々誰かとやりとりする機会は、ぜひもうけてください。
関連記事
この記事を書いた人
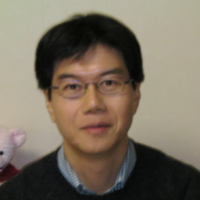
- 都内出版社などでの勤務を経て、北海道の老舗翻訳会社で15年間役員を務める。次期社長になるのが嫌だったのと、寒い土地が苦手で、スピンオフしてフリーランスライターに転向。最近は写真撮影に目覚め、そちらの道も模索する日々を送る。