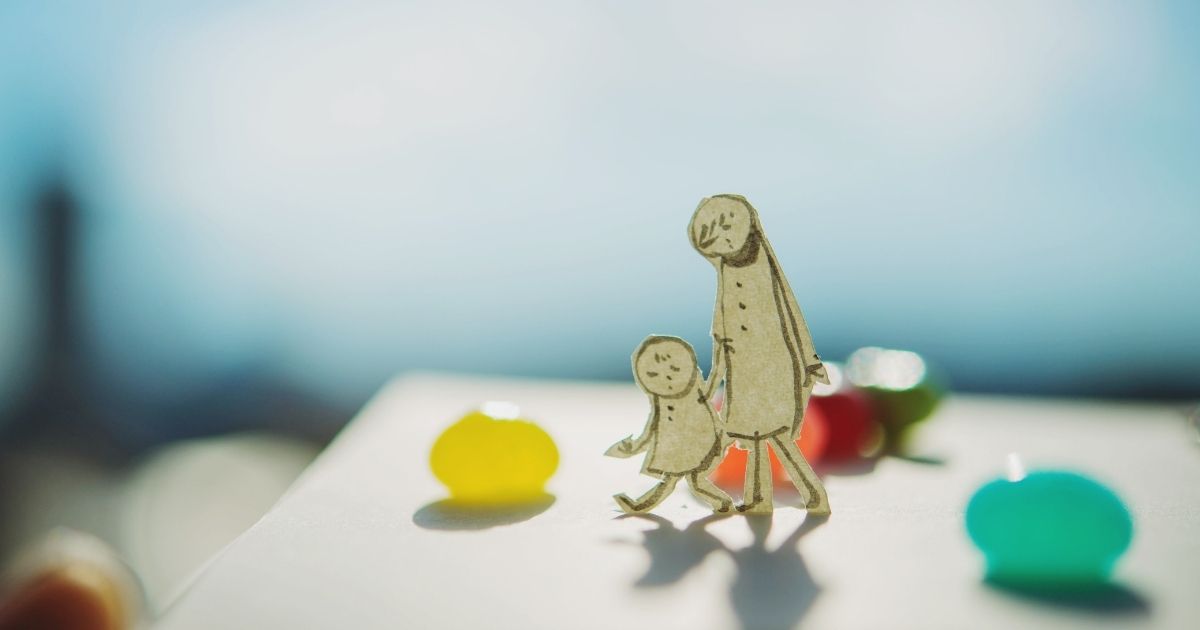“9月1日問題”と向き合う──子どもの不登校に「哲学対話」という選択肢

夏休みがあけ二学期がはじまる9月1日に不登校や自殺が急増する“9月1日問題”。教育学者の苫野一徳さんの「親子で哲学対話」を読み解く。
夏休みが終わる頃、“9月1日問題”という言葉がメディアで取り上げられるようになる。
これは、新学期の始まりとともに、小中高生の自殺が急増する傾向があることを示す言葉だ。実際、内閣府の統計でも、子どもの自殺件数は8月末から9月初旬にかけて顕著に増えるとされており、子どもにとって新学期が心理的な負担となっていることがうかがえる。
背景には、学業への不安や人間関係、学校という空間そのものへの違和感など、さまざまな要因がある。
文部科学省によると、不登校の小中学生は2023年度に34万人を超え、過去最多となった。不登校は決して一部の“特別な問題”ではなく、誰もが当事者になる可能性を示していると言える。
教育者であり哲学者の苫野一徳さんも、自身の家庭でこの問題に直面した経験を持つ。
ある日、小学2年生だった娘が突然「パパ、学校やめたから」と言った。
理由を詳しく語ることはなかった。ただ、“もう行けない”という気持ちが彼女の全身からにじみ出ていたという。
苫野さんは、それ以上理由を詰問したり登校を促したりすることはせず、「ともに問いを考える」という方法に切り替えた。
そこから毎晩10分ほど、娘と哲学対話を始めたのだ。
哲学対話とは、「幸せとは?」「正義とは?」「なぜ学校に行くのか?」といった、正解のない問いについて、他者とともに考える時間を持つ営みである。
教育現場でも徐々に導入が進んでおり、論理的思考力や対話力を育てる方法として注目されている。
家庭で実践する場合は、寝る前のちょっとした時間や食事中の会話など、日常のなかで十分に取り入れられる。
問いは身近なもので構わない。「なぜ嘘はだめなの?」「友達って?」といった素朴な疑問から、対話は始まる。子どもが何気なく聞いてきたことをきっかけにしてもいい。それがなければ、何について話すかを決めてからスタートさせることを苫野さんは推奨する。
苫野さんはこの体験をもとに、『親子で哲学対話』(大和書房)を上梓している。
同書では、家庭内で対話を続けたことで、娘が自分の考えを自分の言葉で語れるようになっていった過程が丁寧に綴られている。
苫野さんはこう語る。
「子どもが問いを持つということは、既に世界を感じ、考えようとしている証です。
大人は答えを与えるのではなく、その問いをともに考える立場に立つことが求められます」
「なぜ学校に行けないのか」と問い詰めるよりも、「あなたは今、何を感じているのか」「なぜそう思うのか」を一緒に掘り下げる時間が、子どもにとっての自己理解や安心感につながる。
哲学対話は、そのための道具のひとつになり得る。
9月1日が近づく今、不登校や“学校に行きづらい”という気持ちを持つ子どもは少なくない。
そのような子どもに対して、登校をゴールとするのではなく、「なぜ行きたくないのか」「学校とは何か」といった問いを共有することで、子ども自身が自分の気持ちや価値観と向き合う機会を持つことができる。
“問い”には即効性はないかもしれない。だが、考える時間を共有したという経験は、子どもの「自分の感じ方は大事にしていい」という感覚を育てていく。
「9月1日問題」は、個々の子どもの問題ではなく、社会の側に突きつけられた課題である。
そのとき、問いを通じて子どもと向き合う哲学対話は、親にとってもひとつの有効な手段となるだろう。
子どもが問いを持つ自由を保障し、それに耳を傾ける。
それは、学校に行く・行かないという二項対立を越えて、子どもが自分らしく生きるための一歩になるのではないだろうか?
文/長谷川恵子
関連記事
この記事を書いた人

- 編集長
- 猫と食べることが大好き。将来は猫カフェを作りたい(本気)。書籍編集者歴が長い。強み:思い付きで行動できる。勝手に人のプロデュースをしたり、コンサルティングをする癖がある。弱み:数字に弱い。おおざっぱなので細かい作業が苦手。